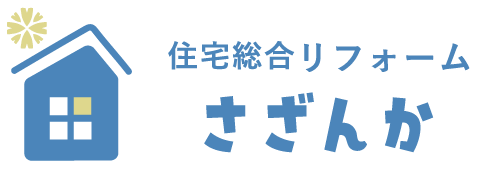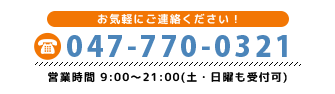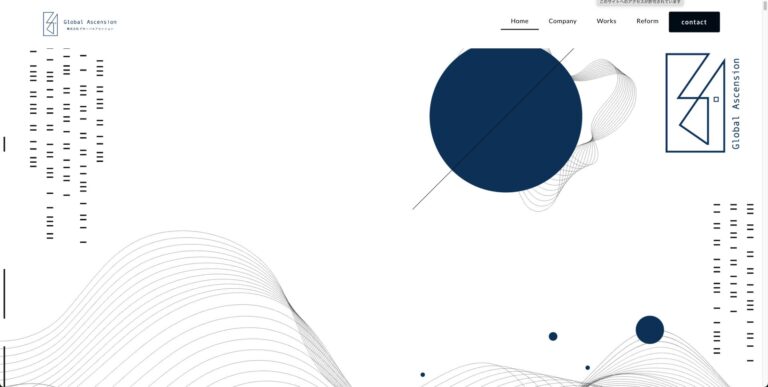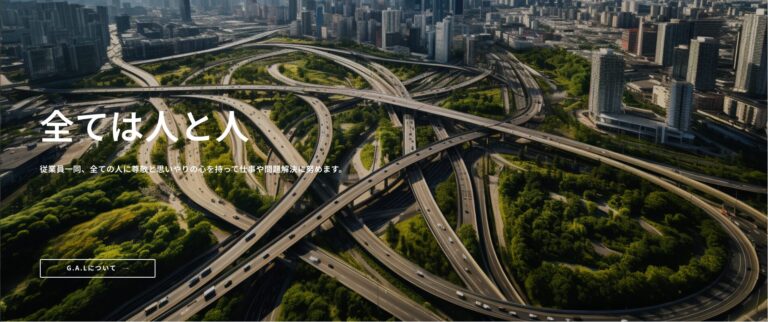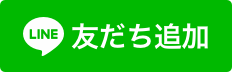外壁や屋根と比べると、意外と見落とされがちな「鉄部」。
ベランダの手すりや柵、雨戸の枠、フェンスなど、金属部分は住まいの随所に存在しています。これらの部位は、紫外線・雨・風・温度変化にさらされるため、劣化が早く、サビや塗膜剥がれが起こりやすい箇所です。
そんな鉄部を守るために欠かせないのが「鉄部塗装」。
今回「住宅総合リフォーム さざんか」が行った施工では、1回目・2回目と塗り重ねる二度塗り仕上げを徹底し、美しく長持ちする塗装を実現しました。
この記事では、鉄部塗装の必要性と二度塗りの意味、実際の施工事例を交えながら詳しくご紹介します。
鉄部はなぜ劣化しやすい?
鉄部は建物を構成する上で欠かせない素材ですが、最大の弱点は「サビやすい」ことです。
劣化の原因
- 雨水や湿気による腐食
- 紫外線による塗膜の分解
- 塩害(沿岸部では塩分でサビが進行)
- 経年劣化での塗膜の剥離
これらが重なると、鉄部は急速にサビていきます。放置すると腐食が進行し、強度が低下して安全性を損なうことも。
鉄部塗装を怠るとどうなる?
鉄部塗装を定期的に行わないと、以下のリスクが発生します。
- サビが進行し、部材が腐食して交換が必要になる
- 塗膜が剥がれ、美観が著しく損なわれる
- サビ汁が外壁や床を汚す
- 構造的に脆くなり、転落防止柵などは危険性が増す
つまり、鉄部塗装は「見た目を整えるため」だけでなく、安全性と耐久性を守るための重要なメンテナンスなのです。
今回の施工事例:二度塗りの鉄部塗装
今回ご紹介するのは、手すり(柵)の鉄部塗装です。
写真にあるように、1回目 → 2回目と丁寧に塗り重ねることで、美しく長持ちする仕上がりになりました。
📸 1回目の塗装
- 下地を整えた後、ローラーで1回目の塗料を塗布。
- サビ止めを兼ねた塗料を使用し、金属を保護。
- この時点ではまだ色にムラがあり、ツヤも控えめ。
📸 2回目の塗装
- 1回目がしっかり乾いた後、仕上げ塗料を塗布。
- ムラが消え、均一でなめらかな塗膜が完成。
- ツヤが増し、美観と耐久性が格段に向上。
鉄部塗装の基本工程
- ケレン作業(下地処理)
サビや古い塗膜を削り落とし、新しい塗料が密着する状態を作ります。 - 下塗り(サビ止め塗料)
鉄部を腐食から守るため、必ずサビ止めを塗布。 - 中塗り(1回目)
色をつけながら塗膜を形成し、強度を高める。 - 上塗り(2回目)
仕上げとして塗布し、色・ツヤ・防水性を整える。
この流れをしっかり守ることで、長持ちする鉄部塗装が可能になります。
二度塗り仕上げが重要な理由
「1回で十分じゃないの?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、実際には二度塗りこそが鉄部塗装の寿命を左右するポイントです。
- 塗膜の厚みを確保できる → 耐久性UP
- 色ムラが消える → 美観性UP
- 塗料の密着性が向上 → 剥がれにくい
- 防錆効果が強化される → サビに強くなる
鉄部塗装のメリット
✅ 耐久性の向上
→ サビ・腐食を防ぎ、鉄部の寿命を延ばします。
✅ 安全性の確保
→ ベランダ柵や手すりなどの強度を維持し、安心して使用可能。
✅ 美観の改善
→ ピカピカに蘇り、建物全体の印象が若返ります。
✅ コスト削減
→ 早期塗装で交換工事を防ぎ、メンテナンス費を節約。
よくある質問 Q&A
Q. 鉄部塗装は何年ごとに必要?
→ 環境によりますが、5〜7年ごとが目安です。特に海沿いや雨の多い地域では短い周期でのメンテナンスがおすすめです。
Q. DIYで塗装しても大丈夫?
→ 表面的には可能ですが、ケレン作業やサビ止めの選定が不十分だとすぐに剥がれます。 長持ちさせるなら、専門業者に依頼するのが安心です。
Q. 外壁や屋根塗装と一緒にできる?
→ はい!足場を組むタイミングで一緒に行うと、費用を抑えられます。
「さざんか」のこだわり
🖌 職人の丁寧な二度塗り仕上げ
→ 一本一本の鉄部に職人の技術を込め、長持ちする仕上がりに。
🔧 徹底した下地処理
→ サビを残さず処理し、塗膜の密着性を最大化。
📷 写真で施工過程をご報告
→ 見えにくい部分も“見える化”で安心。
まとめ
- 鉄部は劣化が早く、サビや腐食を防ぐには塗装が必須
- 二度塗り仕上げで、美観・耐久性・防錆性が大幅に向上
- 定期的な鉄部塗装は、安全性の確保にも直結
- 「さざんか」なら、細部まで丁寧な施工で長持ちする鉄部塗装を実現
🏠 住宅総合リフォーム さざんかでは、
外壁や屋根だけでなく、鉄部塗装も含めたトータルリフォームに対応しています。
「サビが気になる」「柵が古びて見える」
そんな小さなご相談からお気軽にどうぞ😊