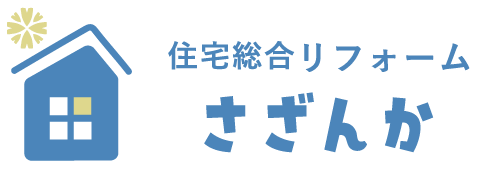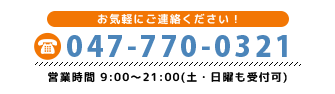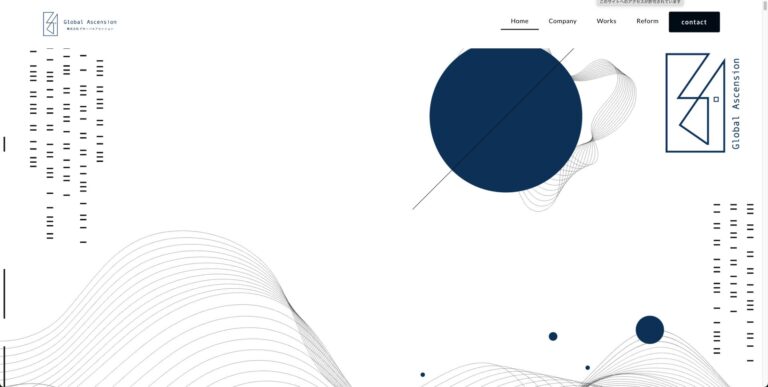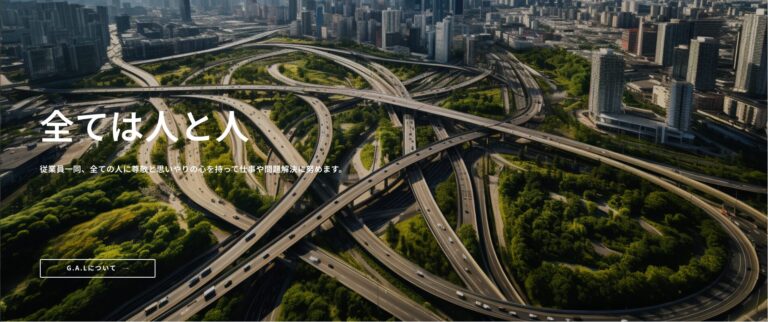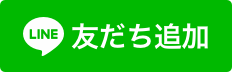Introduction
外壁や屋根の塗装工事では通常、「下塗り」「中塗り」「上塗り」の三度塗り工程が基本です。一回目が下塗り、二回目が中塗り、三回目が上塗りと呼ばれ、それぞれに役割があります 。中でも一般の施主には「中塗り」という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。中塗りとは、塗装の途中で行われる中間の塗装工程のことで、仕上げ塗料を2回に分けて塗るうちの1回目にあたります 。塗料は通常3回塗りを行うことで初めて長持ちする丈夫な塗膜になりますが、もしこの3工程のうち1つでも欠けてしまうと塗膜が弱くなり、剥がれやひび割れなど施工不良の原因になりかねません 。本記事では、この「中塗り」について、初心者の方にも分かるようやさしく解説しながら、その専門的な重要性やポイントを紹介します。中塗りの役割や下塗り・上塗りとの違い、使用される塗料・機材、さらには中塗り段階で起こり得る施工不良と対策、そして施主として確認すべきポイントまで詳しく見ていきましょう。
中塗りとは何か
外壁に中塗り塗料をローラーで塗布している中塗り作業中の様子です。中塗りとは、塗装工事における2番目の塗装工程のことです。下塗り(プライマー塗装)の後に行い、上塗り(仕上げ塗装)を行う前の工程になります 。簡単に言えば、下塗りで整えた下地の上に、仕上げ用の塗料を一度塗る作業です。この中塗りによって一度仕上げ塗料を塗り、その上にさらにもう一度仕上げ塗料を重ねる(二度塗りする)ことで、最終的な塗膜の厚みや美しさを確保します 。中塗りまで塗った段階でも壁面はほぼ選んだ色に覆われて一見きれいに仕上がったように見えます。しかし中塗りだけでは微妙な色ムラや塗り残しが生じることもあるため、最終的に上塗りを行って仕上げとするのです 。
下塗り・上塗りとの違い
塗装の三工程である下塗り・中塗り・上塗りは、それぞれ目的や使う塗料が異なります。下塗りとは、一番最初に行う塗装で、下地処理の一環として塗料の密着を高める接着剤のような役割を持つ工程です 。下塗りにはシーラーやフィラー、プライマーといった下塗り専用の塗料を使い、古い外壁と新しい塗料をしっかり密着させる下地を作ります 。下塗り剤は上塗り材とは成分も機能も異なり、白や透明など仕上げの発色を良くする色が用いられることが多いです 。
それに対して上塗りは最後の仕上げ塗装であり、選んだ色・艶(つや)・機能を発現させる工程です 。上塗りでは耐候性(雨風や紫外線に対する強さ)や防水性、低汚染性など、完成後に外壁を保護する性能を持つ塗料を塗り、美しい外観に仕上げます 。上塗りは中塗りと同じ塗料を用いて行われ、中塗りで生じた塗りムラを隠して均一な色に整えるとともに、塗膜に所定の厚みを持たせて耐久性を高める役割を担います 。
中塗りはこの下塗りと上塗りをつなぐ中間の工程です。使用する塗料は基本的に上塗りと同じ仕上げ用塗料を使うのが一般的です 。下塗りで作った下地の上に仕上げ用塗料を一度塗り重ねることで、下地が透けて見えないように色を付け、上塗りの発色と定着を良くする下地層の役割を果たします 。中塗りと上塗りの2回に分けて仕上げ塗料を塗ることで、結果的に塗膜全体の厚みが十分に確保され、長持ちする塗装となるのです 。
まとめると、下塗りは接着と下地調整、中塗りは色乗せと厚みづくり、上塗りは美観と最終保護という違いがあります。それぞれ欠かせない工程であり、一つでも省略すると塗料本来の性能を十分に発揮できなくなってしまいます 。
中塗りの役割と効果
中塗りには塗装全体の品質を左右する重要な役割がいくつもあります。専門的に見ると、中塗り工程には主に次のような目的・効果があります。
- **塗膜に厚みを持たせ、耐久性を向上させる。**中塗りで仕上げ塗料を一度塗り重ねておくことで、最終的な塗膜厚が十分に確保されます。塗膜が厚いほど紫外線や雨風など外的ダメージに強くなり、塗装の耐久性や防水性が向上します 。逆に塗膜が薄いままだと、せっかく高品質な塗料を使っても外壁を十分に保護できず、早期に劣化してしまう恐れがあります。
- 色ムラを防ぎ、美しい仕上がりにする。塗装では塗料を均一に行き渡らせることが肝心です。中塗りを挟んでから上塗りをすることで、下地の色が透けたり一度塗りでは生じがちな色ムラを抑える効果があります 。特に、鮮やかな色を塗る場合や、もとの色から大きく色替えする場合は一度塗りでは発色が不十分なので、中塗りによって発色を良くし上塗りの見栄えを整える下地とすることが重要です 。
- 下塗りと上塗りを結合させ、塗膜の密着力を高める。中塗りは、下地と上塗りの架け橋となる接着層として機能します 。下塗り材で下地を整えただけではまだ塗膜は薄く脆弱です。中塗りで仕上げ用塗料を一層設けることで、下塗り材の上に強固な塗膜の土台を作り、後から塗る上塗りがより剥がれにくくなる効果があります 。このように、中塗りを挟むことで塗料同士がしっかり層を成し、一体化した強い塗膜になるのです。
以上のように、中塗りは仕上がりの美しさと塗装の長持ちの両方に大きく寄与する重要な工程です。言い換えれば、中塗りを丁寧に行うかどうかで最終的な塗装の品質が決まると言っても過言ではありません。
使用される塗料や機材
中塗りに使用する塗料は、多くの場合上塗り(仕上げ)と同じ塗料が使われます 。たとえば外壁塗装でシリコン塗料を仕上げに選んだ場合、中塗りでも同じシリコン塗料を用いて色を付けていきます。これは、中塗りと上塗りで異なる塗料を使うと材料間の密着や発色に差が出る可能性があるためで、同じ塗料を重ねることで安定した仕上がりになるからです。なお塗装仕様によっては、中塗り専用に開発された塗料(中塗り材)を使うケースもあります 。たとえば下塗り材と上塗り材の相性を高めるバインダーのような中間塗料や、厚膜を形成するための専用中塗り材を併用する特殊な工法もあります。ただし一般的な戸建て外壁塗装では、下塗り専用材の後は仕上げ塗料を2回塗り重ねるケースが主流です 。
中塗りに用いる機材や道具は基本的に上塗りと同様です。広い外壁面には毛丈(けたけ)の長いローラーを使って塗料を塗布するのが一般的で、細部や縁(ふち)などローラーが届かない部分は刷毛(はけ)を用いて塗ります。ローラー塗装は塗料をたっぷり載せられるため中塗りで必要な厚みを確保しやすく、また凹凸のある外壁にも塗り残しなく塗料を行き渡らせることができます。場合によってはスプレーガン(吹き付け)で中塗り・上塗りを行うこともありますが、一般住宅では飛散のリスクなどからローラー施工が主流です。中塗り塗装を行う際には、他の部位を汚さないようビニールシートやマスキングテープで養生(ようじょう)し、必要に応じて専用の攪拌機(ミキサー)で塗料を均一に混ぜてから塗布します。使用する塗料缶は上塗り用と同じものなので、施工後に塗料の空き缶を施主に見せて確認してもらう業者もいます。そうすることで、契約どおりの塗料を規定量使った中塗り・上塗りが実施されたかを施主自身が把握でき、安心につながるでしょう。
中塗りで起こりうる施工不良とその対策
塗装工事では、中塗りの段階で手抜きやミスがあると最終仕上がりに影響が出ます。ここでは、中塗りで起こり得る代表的な施工不良の例と、その対策について解説します。
- 中塗り工程の省略(手抜き工事) – 悪徳な業者の中には、本来必要な中塗りを省いて下塗り後に1回しか上塗りをしないケースがあります 。塗装は規定の3回塗りをしなければ十分な厚みや密着力が得られず、こうした手抜き工事では短期間で塗膜の剥がれや退色などの不具合が発生します 。対策としては、必ず3回塗りを行う業者を選ぶこと、契約書や見積書に塗装回数が明記されているか確認することが重要です 。施工中も、中塗りが確実に施工されたか写真を撮ってもらったり、自分の目で工程を見せてもらったりすると安心です。
- 塗料の乾燥不足による密着不良 – 下塗りや中塗りの塗料がまだ十分乾いていないうちに次の上塗り工程に進んでしまうと、塗膜内部に湿気や溶剤分が残って密着不良を起こします 。具体的には、塗装面がベタついたり後から塗った塗料が下地とともに剥離したり、あるいは乾燥過程でひび割れが生じることがあります。対策として、各工程間でメーカー指定の乾燥時間を必ず守ることが挙げられます 。プロの塗装業者は気温や湿度に応じて適切なインターバル(乾燥養生期間)を確保しますが, 施主としても雨天や低温時に無理な塗装をしていないか注意しましょう。もし天候不良でやむを得ず途中で塗装を中断した場合は、天気が回復して十分乾燥してから再開するのが望ましいです。
- 塗布量不足や一回厚塗りによる仕上がり不良 – 塗料には「1回の塗装で何㎡に何リットル塗れるか」という規定の塗布量があります 。例えば1㎡あたり0.2Lまで、といった決められた量以上に一度に厚く塗ろうとしても、塗料は均一に膜を形成できず本来の性能を発揮できません 。中塗りを省略して上塗りだけで厚く塗ろうとしたり、適正量より少ない塗料で広い面積を塗り伸ばしたりすると、結果として規定厚みに満たない脆弱な塗膜となり耐久年数が大幅に低下します。対策として、中塗りと上塗りの2回に分けて適切な量の塗料を塗り重ねることが絶対条件です 。見積り段階で使用する塗料缶の本数や塗布量が明示されているか確認し、必要量をしっかり使ってもらえる業者かチェックしましょう 。施工後すぐに下地が透けて見える箇所や色ムラが残っている場合は、中塗りあるいは上塗りの塗布量不足が疑われます。その場合は手直しとして追加塗装してもらう必要があります。
- その他の中塗り段階の不良 – 中塗りでは他にも、塗り残し(塗りムラ)や塗料の垂れ・たまりといった施工ミスが起こる場合があります。ローラーでの塗装時に同じ所を何度も往復しすぎると塗料が部分的に厚く付きすぎて垂れ(液だれ)やローラー跡の模様が残ることがあります。また逆に狭い範囲を横着して薄く伸ばしすぎると塗り残しや透けが発生します。こうした不良があると上塗りをしても跡が残ったり凹凸になったりするため、職人は中塗りの段階でムラなく均一に塗るよう注意深く作業します。対策として、中塗り後に職人や現場監督が入念にチェックを行い、垂れやムラがあれば乾燥後に研磨して再塗装する処置が必要です。施主も足場に上がらずとも地上から見える範囲で構いませんので、中塗り後の様子を確認し、異常がないか気になる点があれば遠慮なく指摘すると良いでしょう。
施主ができるチェックポイント
塗装工事を依頼する際、施主として中塗り工程について確認しておくべきポイントをまとめます。以下の点を押さえておけば、手抜きや不良施工を未然に防ぎ、安心して工事を任せることができるでしょう。
- 契約内容の確認: 見積書や契約書に「下塗り・中塗り・上塗り」の3工程が明記されているか確認しましょう。中塗りを含めた3回塗りが記載されていない場合は、業者に塗装仕様を問い合わせる必要があります。また、使用する塗料の種類や缶数、塗布量も記載があるとなお安心です 。
- 2回塗りで十分と言われていないか: 業者から「高性能な塗料だから下塗りと上塗りの2回で大丈夫」「下塗り不要の塗料がある」などと言われた場合は注意が必要です 。基本的にほとんどの塗料は3回塗りが前提であり、メーカーも規定通りの塗装回数を推奨しています 。2回塗りで済ませようとする提案は手抜きの可能性があるため、そのような説明を受けたら他社の意見も聞いてみるなど慎重に判断しましょう。
- 中塗りと上塗りの色分け: 信頼できる業者であれば中塗りと上塗りを同じ色で仕上げるのが一般的ですが、もし工事に不安がある場合は中塗りと上塗りでわざと色を変えてもらう方法もあります 。中塗りと最終色を少し変えることで、ちゃんと2回塗り重ねたか誰の目にも判別しやすくなります 。例えば下塗りが透明なら中塗りは薄いグレー、上塗りは選んだ最終色とするなどです 。色に差をつけておけば、仮に中塗りを怠ればすぐわかりますし、施工ミスの防止や万一の手抜き抑止にも役立ちます。ただし最終的な仕上がりに影響しない程度の色差に留める必要があり、上塗りできちんと隠れる色選定にすることがポイントです。信頼できる職人の場合は無理に色を変えなくても問題ありませんが、施主側で把握したい場合の一つの工夫と言えます。
- 施工過程の記録: 工事中の様子を写真に撮ってもらうよう依頼しましょう。特に下塗り・中塗り・上塗りそれぞれ完了時の写真があれば、後から施工内容を確認できます。多くの塗装業者は施工報告書として工程ごとの写真を提供してくれます。写真があれば「本当に中塗りまで施工されたか」を施主自身でも確認でき、万一仕上がり後に問題が見つかった際の資料にもなります。記録を残すことは業者にとっても誠実な仕事の証明になります。
- 現場でのチェック: 時間が許すなら施工期間中に現場を見に行きましょう。もちろん足場に登る必要はありませんが、地上から職人に声をかけて途中経過を見せてもらったり、乾燥中の壁の状態を確認したりできます。下塗り後の状態(下塗り材の色がついているか)、中塗り後の色合い(選んだ色が一度塗りでどう発色しているか)などを自分の目で見ることで、工程が省略されていないか把握できます。職人に質問すれば丁寧に説明してくれるでしょうし、熱心に見守る施主がいれば業者側も手を抜けないものです。
- 仕上がり確認: 最終的に塗装完了後の仕上がりを自分でもチェックしましょう。外壁全体を見渡して、色ムラや塗り残しがないか、艶や手触りに異常がないか確認します。中塗りが適切に行われていれば、上塗りだけでは隠しきれない下地の透けや色ムラが現れることなく、美しく均一な仕上がりになっているはずです。万一気になる箇所があれば遠慮せず指摘し、必要に応じて追加の上塗りや補修をしてもらいましょう。
まとめ
「中塗り」は外壁塗装において一見地味な中間工程ですが、耐久性と美観を両立させる要となる非常に重要な工程です。下塗り・中塗り・上塗りの各工程が揃って初めて強固で長持ちする塗膜が形成されます 。特に中塗りは仕上げ用塗料を2回に分けて塗る中で最初の一層目を作る作業であり、これを丁寧に行うことで最終的な発色や塗膜の厚みが大きく向上します。裏を返せば、中塗りを省略したり粗雑に済ませたりすると、どんな高性能な塗料でも本来の性能を発揮できず、塗装の寿命が短くなってしまいます 。施主としても中塗りの重要性を理解し、信頼できる業者に適切な工程で施工してもらうことが大切です。
塗装工事を依頼する際には、本記事で紹介したポイントをぜひ参考にしてください。中塗りを含む三回塗りがしっかり実施され、乾燥時間や塗布量など基本を守った施工であれば、美しく仕上がるだけでなく何年経っても塗膜が剥がれにくい満足のいく外壁リフォームとなるでしょう 。大切なマイホームを守る塗装ですから、中塗りの重要性を再確認し、安心して任せられるプロの手で長持ちする塗装を実現しましょう。